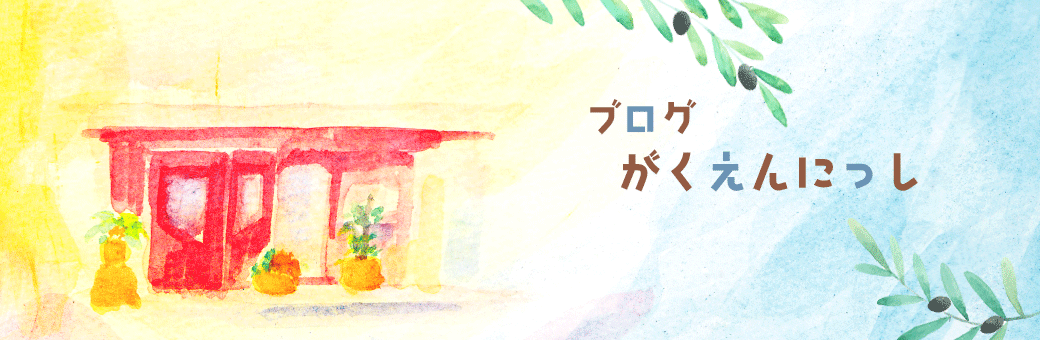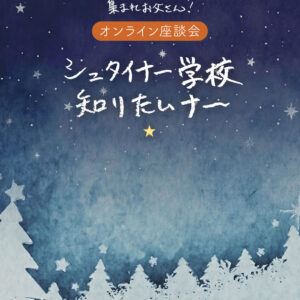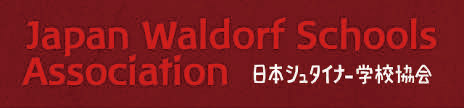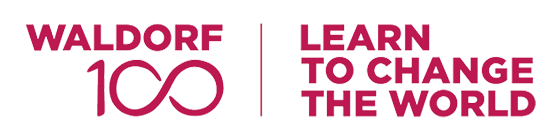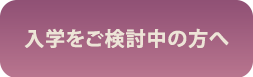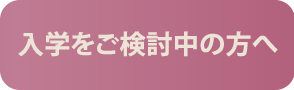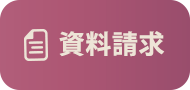3年生は「くらしとしごと」の授業の一環で、近隣の農家さんにお借りしている田んぼで毎年稲作に取り組んでいます。田植えをし、草取りをし、夏休みには稲の花を観察。
そして、先日は稲刈りがありました。

刈った稲を校庭に1週間ほどはざかけしたのちに、脱穀です。今回はその様子をお伝えします。


校庭にずらりと並ぶたわわに実った稲。いつもお世話になっている「にいはる里山交流センター」へと運び出します。
子どもたちの手渡しリレーで、つぎつぎと車のトランクに収めていきました。
この日は天気にめぐまれ、10月にして最高気温29℃。汗ばむ陽気の中、学園から森の道を歩いてにいはる里山交流センターに到着。交流センターの方から説明を受けます。
班に分かれて、保護者の方たちのサポートのもと、千歯こきという道具を使って、穂をそぎ落としていきます。足で道具を固定しながら、稲穂を歯にあてがって引っ張ります。しっかり握っていないとするすると稲が抜け落ちてしまう。力のいる作業です。


穂と藁が入り混じった状態のものを、唐箕(とうみ)という道具で「選別」します。ハンドルをぐるぐる回してファンで風を起こし、上から少しずつお米を落としていくと、軽い藁や中身が小さい穂は風で吹き飛ばされて、重い穂だけが下に落ちて溜まっていく仕組みです。
一人ではむずかしい作業なので、息を合わせ、声をかけ合う協力が必要です。


溜まった重い穂を米袋に収めていきます。穂をそぎ落としたあとの藁は「家づくり」に活用するため、先生方がどんどん束ねていきます。
 こく、分ける、収める、束ねる。ひたすらにこの工程がリズムをともなって、ある種のグルーブが生まれていきました。
こく、分ける、収める、束ねる。ひたすらにこの工程がリズムをともなって、ある種のグルーブが生まれていきました。
手際よく取り組み、予定よりも早くすべての稲を脱穀・選別できました!
お米と藁を学園に持ち帰って、今後の活動に備えます。
学園がお借りしている田んぼの環境について、交流センターの方からうかがったお話が興味深かったです。お借りしている田んぼは、スズメが来ないそうです。なぜなら、近辺の生態系の頂点に猛禽類の鳥がいるからとのこと。だからスズメ避けをしなくてもかかしを立てなくても大丈夫。
3年生の子どもたちにはまだ早い学びなので、大人向けにこっそり教えていただきました。

自然豊かな環境から学ぶことがたくさんあります。
横浜は都会のイメージが強いですが、ここ緑区には豊かな自然と人とが共生する環境があります。
その恩恵を、子どもたちも大人たちも体いっぱいに享受できるありがたみをあらためて感じたのでした。
3年生保護者 おはよー