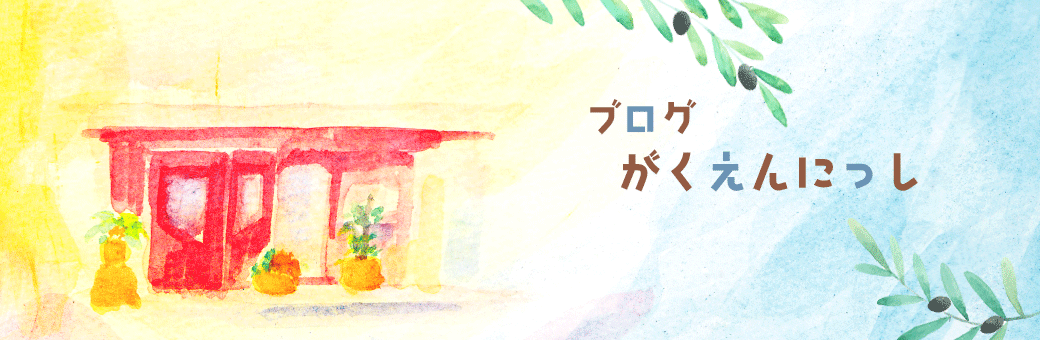2月3日と4日、鶴見公会堂で横浜シュタイナー学園の8年生劇を行いました。
これまでの学びの集大成ともいうべき8年生を担任教師が振り返りました。想いの込もった長編です。どうぞお読みください。(広報の会)
1学期の終わりに本を決め、2学期から本格的に準備と練習に取り組み始めた8年生劇。その全体を振り返ってみると、改めてこの8年生劇が今まで学んできたことを活かした総合芸術であることに気づく。
劇の取り組みを念頭におき、1学期は朝のリズムの時間に特に朗誦に力を入れた。題材は、『走れメロス』。生徒たちも、すでに今年度は劇をやるということ、2月にその発表をするということが分かっており、朗誦に取り組む様子はとても意欲的だった。いかに感情をこめて言葉を言うか、そして、はっきりと聞こえる声を出すかということに意識を向けた。クラスのほとんどの子が、劇を楽しみにし「成功させたい」「達成感を味わいたい」という気持ちを持っていることがひしひしと伝わってきた。もちろん、生徒たちの中には劇は苦手という子もいたが、その子の様子も2学期に入るとだんだんに変わっていき、前向きな姿で練習に取り組み自ら動作の工夫をするようになった。

8年生劇の意義は、その年齢の心理的発達段階に合った目的、すなわち登場人物の人生の一部を感情とともに表現するということにあるが、同時にクラス全員で一つのものを創り出すことにもある。それぞれが自分の力を出し協力して劇を創る過程にこそ、生徒たちを成長させるものがある。役作りをし演ずる中で、担当する仕事を友だちと話し合い行っていく中で、生徒たちは内的にも葛藤を経験する。自分のことだけを考えるのではなく、自分の欲に打ち克つ必要もあり、皆で一つのものを創るということがどういうことであるかを生徒たちは学ぶのだ。
2学期になって劇の準備を始める前にクラスで話し合ったことは、何を大事にしていきたいか、劇創りを通して何を目指したいかということだった。そこでまず出てきたのは、「輪」を大事にしたいということ。それをより分かりやすく言うと、劇作りは「チームワーク」であること、大変さも嬉しいことも皆で「分かち合い」そして「信頼」しあえるようにという意味だと、意見がまとまった。

それから、いよいよ本読み、配役、係分担、練習、準備といろいろな活動が始まった。その中では、辛さや大変さを体験したり、気持ちを切り替え前向きに仕事に取り組んだり、友だちどうし励まし合ったりする生徒たちの姿が見られた。劇創りが進んでいくと、一人ひとりが自分の仕事を責任もって行っている様子、楽しそうに大道具や小道具を作る様子が見られるようになった。小道具係も大道具係も作業計画を立てこつこつと作業を続けた。小道具は剣や財布や槍などたくさんあったが、放課後残れる日は必ず誰かが残って丁寧に作業をしていた。大道具係も小道具係同様、誰かが必ず残って作業を続けた。しかし、大道具の作業は作る衝立の数も多く大道具係3人ではとても大変だった。そこで、それに気づいた他の係の生徒たちも自主的に大道具係の作業を手伝うようになった。衣装係の生徒たちは、放課後、先輩たちが作った衣装を倉庫から出してきて、どんな衣装があるか確認する作業を自主的に行い、各役の衣装をデザインする作業を私や柳本先生に相談しながら行った。音楽係は楽譜集や鈴木先生がくださった楽譜から前奏曲や、場面転換の際に演奏する曲を選び、誰がその曲の演奏を担当できるかも考え分担表を作った。図書館に行ってシェイクスピア劇の音楽についての本から、『十二夜』で使われた曲を見つけてきた子もいる。そして、劇の最後に歌う曲を合唱曲に編曲したのも音楽係であり、それも、そのほうがいいと思った生徒が自ら行ったのだ。広報係の活躍も素晴らしかった。メンバー4人とも、広報の仕事が好きなのがよく分かる仕事ぶりで、それぞれが書いてきた原稿はどれも丁寧に考えられたものだった。実は、当日配るプログラムを印刷した際、よく写っていない箇所や印刷範囲の外になってしまい抜け落ちた文字もあった。私は残念だがしょうがないと思ったのだが、本番の前日に自主練習をするつもりで放課後残っていた生徒たちのうち一人が、どうしても写っていない箇所を書き加えたいと言い、他の子たちもそれに賛同して350部すべてに手を加えた。その作業はそこにいた生徒たちの見事な連携でやりとげられた。
また、冬休み前に皆の劇に向かう意気を高めるためにも、皆の団結のためにも是非合宿をやりたいという声があがり、生徒たちの立案でそれが実施できたのも彼らの自信につながったであろう。

最後に、演技練習の様子にも触れておく。生徒たちは、それぞれの役について生い立ちを想像し、それぞれの人物がいろいろなことを経験したうえで今この舞台にいるのだと考えるようにした。そして、舞台袖でも彼らの生活は続いているのだと思うよう促した。練習の中では、お互いに気づいたことを言い合ったり助言し合ったりする時間をとった。すると、皆が熱心に友だちの演技をみて率直に意見を出し合う様子が見られ、一人ひとりがよりよい劇にしようと思っていることが感じられた。
特に私の印象に残っているのは、演技をするのが苦手な生徒がとても前向きに練習に取り組み、素直に助言を受け入れ、声も大きくなり自ら動きの工夫をするなど変わっていったことだ。そして、一緒に演技をする友だちが、練習の度に心から「すごくよくなったよ。いい!」と賞賛の声をかける姿を見たとき、私にはそのやりとりが本当に嬉しかった。
そして、何より私が嬉しかったのは、舞台の上で全員が輝いていたということ、一人ひとりの存在がはっきりと感じられたということだ。特に、台詞がないときの演技はとても難しい。舞台で劇をしたことのある方ならお分かりだと思う。台詞がなくても、その人物の生活はそこにあるのだから、必ずその人物の物語があるのだ。それを演ずるためには、その人物は何を考え、何をしようとしているのか想像力を働かせなければならない。劇『十二夜』の中で、生徒たちは台詞がなくてもそこに自分はその人物として生きているのだということを心に留め、その人物として演じていた。だからこそ、舞台上の演技に深みが増すとともに、皆が舞台の上で存在感をあらわし輝けたのだと思う。
私が一番気に入っているのは、第5幕でヴァイオラ(シザーリオ)の双子の兄セバスチャンが現れる場面だ。ヴァイオラとそっくりなセバスチャンの登場に、舞台の空気が変わるところ。舞台上の人物たちがその二人を見て驚きを隠せない、その意識を皆が持つだけで空気が変わる。それができる生徒たちを見て、「これはオイリュトミーのおかげ?」と内心思ったのだ。
このように8年生劇を振り返ったとき、生徒たちは自分たちが劇を創るのだという気持ちで活動していたことを思い出す。私に促されてやるのではなく、彼らは自分たちの内からの熱意で動いていた。これこそ、シュタイナー学校の生徒という感じだ。
(8年生担任 神田ひとみ)